日本語教育関係書籍の読書メモ ①
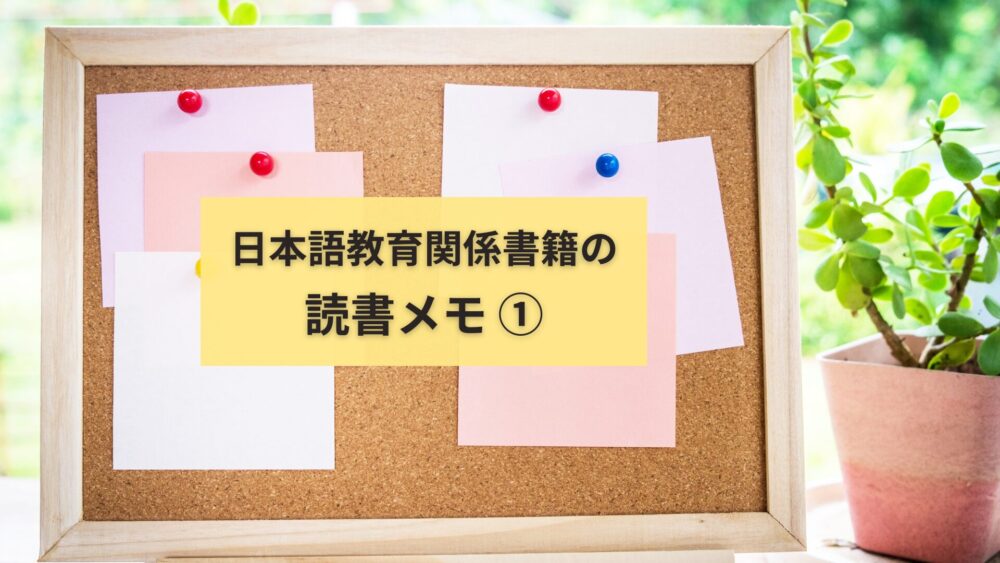
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれます
年末にX(旧Twitter)で過去の投稿を遡って「ああ、そういえばこんな本も読んだなあ」と懐かしくなりました。Twitterのころの投稿が多く、最近は本を読んでもあまりポストしていませんでした。やっぱり記録していないと、いろいろ忘れちゃいますね。
そこで、昔の投稿やメモを掘り起こして、このページにまとめてみました。本の紹介というより、自分用のメモですが、よろしければ最後までお付き合いください。
以前こんな記事も書いています。こちらは「こんな時にこの教材がおすすめ」という感じで書いたものです。
以下の目次をご覧いただくとわかるように、書籍のテーマによる分類というより、自分にとってどんなふうに役立っているのか、という視点で分類してみました。
過去にX(旧Twitter)で投稿したものは、そのまま引用しているので、文体がバラバラですが……当時の記録ということでご容赦くださいませ。
「何を教えるか」のヒントになった本
以下で紹介する3冊は、手に取ったきっかけはいろいろですが、いずれも結果的には「何を教えるか」を考える際のヒントになっている本です。
便宜上「教える」と書きましたが、「授業や教材で何を扱うか」ぐらいのイメージで読んでいただければと思います。
コミュニケーションのための日本語教育文法
読解や聴解における「予測ストラテジー」に興味があり、購入した本です。
「文法」という広い括りではなく、「聞くための日本語教育文法」「読むための日本語教育文法」というように、スキル別にまとめられていいます。
授業や教材でどんなことを扱うべきか考えるときに参考にしています。
プロフィシェンシーから見た日本語教育文法
「使用語彙と理解語彙」を区別して論じられることは珍しくありませんが、「使用文法と理解文法」の区別はないのかなあ?と思って調べていたときに見つけた本です。
p.137に次のような記述があります。
「使用文法と理解文法は別物であり、それぞれ独自の体系を考えなければならない」。
ネットで「使用文法」「理解文法」という用語をネットで検索してみたところ、それほど広くは使われていないようですが、教室活動を考える上でも、2つを区別して考えることは大切だと思っています。
第6章の「難易度を考慮した初級文法の体系」というのも興味深く読みました。
日本語教育はどこへ向かうのか ―移民時代の政策を動かすために
政策の話や大学側の事情など、自分が知らなかった話がいろいろ書いてあり興味深く読んだ本です。なかでも一番印象に残ったのは第2章です。
第2章は庵先生によるもので、「文法シラバスの見直しの必要性と新しい文法シラバス」という項目があり、その中に以下のような記述があります。
・「文法シラバスを見直す上で、まず考えるべきは、理解レベルと産出レベルの区別です」p.67
・「同じ文法カテゴリーに属するものは一つだけにする」(たとえば、「条件」を表す項目は「たら」だけにする)といった…」p.70
時間が限られるコースなどで、文法を絞り込みたい場合、庵先生が提案されている「最低限必要な文型」(p.72)は参考になると思います。(具体的な文型一覧は、本書には掲載されていませんが……)
コンテントベースのデザインレシピ―学習者の批判的思考を促す日本語の授業
Xで紹介されているのを見て購入しました。第2部の実践編はまだ読んでいないのですが、3章までおもしろくて一気に読みました。マニュアルとレシピの違いに関する先生のお考え、失敗談の共有などが特に印象に残っています。
ビジネス日本語 教え方&働き方ガイド
ビジネス日本語以外の授業デザインでも、本書で得た視点で考えると、いろいろアイデアが広がります。実践例が数多く紹介されているだけでも有難いのですが、テキストの選定理由が具体的に書いてあるのも参考になります。
教室活動のヒントになった本
日本語教師のための実践・読解指導
2020年10月のポストより
1章「誤読の読解指導」には誤読の例がいろいろ。
理解過程を知るのはやっぱりおもしろい。
「誤読」は問いかけ作りのヒントにもなる。
ことばの意味を教える教師のためのヒント集: 気持ちを表すことば編
気持ちを表すことばの中には教えにくいなあと思うものがけっこうあります。この本は、場面例(どんな場面で、その言葉を使うのか)が豊富。たとえば、「イライラする」はどんな場面で使うのか、など。
協働学習で学ぶスピーチ
2018年12月のポストより
ネット上の「活動のヒント集」が充実。
http://bonjinsha.com/wp/speech
スピーチ指導に限らず、いろいろヒントがもらえる。グループでスウジコショウカイ(自分を表す数字を使って話す)を実施。反省点もあるけどやってよかった。
<私の例>11回:これまでに引っ越しした回数
文章は接続詞で決まる
接続詞「なぜなら」についての以下の記述が特に印象に残っています。
「私はふだん留学生に日本語を教える仕事をしているのですが、作文の添削のさいに、この「なぜなら」系の接続詞をいかに削るかに日々苦心しています。」
この引用部分、私も作文指導のときに、「なぜなら」を使う練習をしていたので、耳の痛い指摘です。教材や指導の影響もあるのかも、と思いました。
自分の〈ことば〉をつくる あなたにしか語れないことを表現する技術
2024年4月のポストより
「〇〇と私」というタイトルでレポートを書く活動
最後のエピソード部分
ひとりの高校生がクラスメイトとのやり取りを通じて、気づきを得て、レポートを仕上げていく過程が印象に残った。記述も具体的でイメージしやすい。
その他
日本語教師のためのはじめてのコーチング
2023年2月のポストより
「質問されることで、新たな視点を得ることができ、気づきにつながります。」p.38
書籍中の質問を自分自身にしながら、これを実感しました。
・「実行しなかった場合は何が妨げになったのか」 p.68
・「うまくいったときもあるか」 p.99
・「今のスコアを10%上げるために、どんなことができるか」 p.96
今の私に響いた質問です。「スコア」「10%」はいろいろな言葉に置き換えてみました。
ちなみに、Kindle版は固定レイアウトですが、読みやすかったです。
日本語教育学のデザイン ―その地と図を描く
2018年11月のポストより
連日の外国人財受け入れ関連のニュース。改めて『日本語教育学のデザイン』をパラパラと。少し前にこの本を読んで「日本語教育関係者の社会的役割」について考えるきっかけをもらった。自分にはその視点が十分ではなかったと気づいた。気づいただけでも一歩前進かな…
自分のメモ的なものを並べた記事になってしまいましたが、何かの参考になればうれしいです。
最後にこの記事を書いてみての振り返りを残しておきたいと思います。
私は、本の紹介を聞いたりするのが好きです。特に「その本を手に取ったきっかけ」「印象に残った点」「本の内容が自分とどうつながるのか」といった話を聞くと、興味をそそられます。
これからは、そういった視点も意識しながら、読書メモを残していきたいなと思っています。
いくつか読書メモがたまったら、またブログにアップしようと思って、今回のタイトルは①を入れてみました。②を書く日はいつになるでしょう(笑)
